当ブログは皆様の投資判断に役立つような情報を体系的にお伝えすることを目的としています
皆様ご無沙汰しております。
読者数もまだまだの当ブログですが久しぶりの投稿ということで、まずはご挨拶から。
前回までの【経済的な堀】シリーズでは「将来的に利益を稼ぎ続ける会社が持っている”経済的な堀”」について解説をしていきました。
今回の【MBAバリュエーション】シリーズからは、
企業総価値>時価総額であれば、その会社は割安な状態と考えられる
以上に基づいて会社全体の価値、企業総価値の算出方法に踏み込んでいきたいと思います。
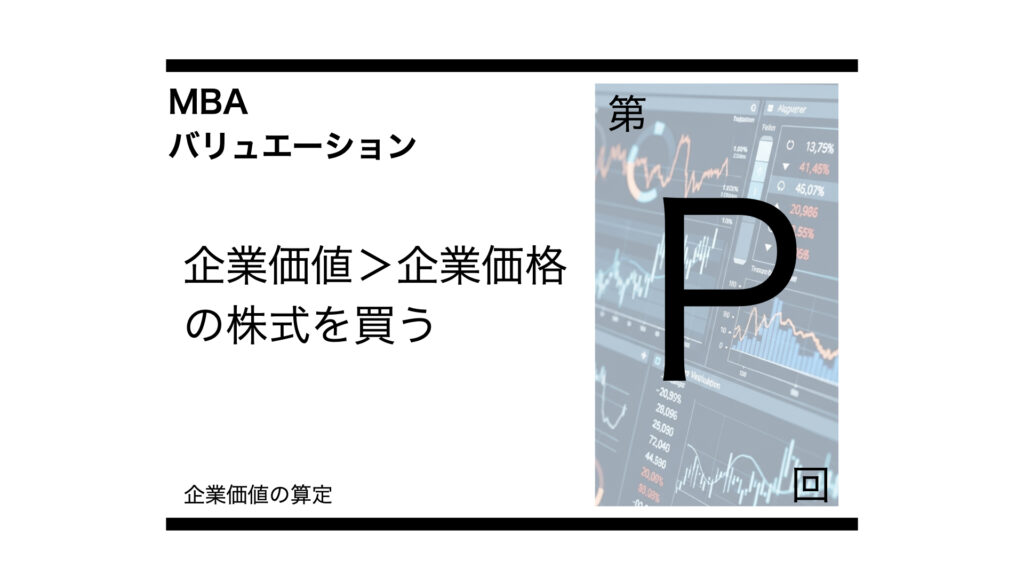
私も以前は、経済的な堀の確認と、簡易的に想定株価を算出することで投資判断を行なっておりましたが下のような違和感がありました。
・算出される想定株価が市場価格と乖離してのはなぜか(結果が安過ぎる、高過ぎる)
・業界や会社毎に成長性やリスク性が異なるのに、一律の指標を当てはめて計算して良いのか
例えば、製薬業界と情報通信業界では商品の販売方法、資金回収までの期間や、会社の資産構成も異なるため一律に比較はできません。
こういった状況は、投資の判断に「迷いと疑問」を抱えて購入することになり、
私が一番重視する「納得して購入する(=ある程度買う理由をつける)」ことの難しさにも繋がるからです。
また納得して購入していない株式は市況の上下によってすぐに売買してしまうことや、どの程度の期間ホールドすれば良いかの判断材料も得られず、株式投資の利益を得ることも遠くなってしまうでしょう
よって再度、企業総価値>時価総額であることで割安性を判断できるよう、算出方法をまとめることに致しました。
大まかな割安性の確認の流れは「現状」ではこの手順で考えています。
【 手 順 】
1,経済的な堀の確認
→無形資産、乗り換えコスト、ネットワーク効果、コスト・規模の優位性の判定
2,財務指標の確認、簡易株価分析
→割安性、収益性、成長性の確認、簡易的に株価の分析を行います。
3,購入検討の企業と、その競合企業の分析
→企業総価値、EBITDAやPBR、PER等の諸倍率を購入検討の企業、競合他社で比較します。
4,分析3のまとめを行います
5,5年先の収支計画を作成し企業総価値を想定。現在価値に割り戻します。
→過去の収益伸び率などを参考に企業総価値とFCFを想定します
6,購入の最終判断
→手順1~5をまとめます。
割安か、または企業総価値>時価総額となっているかな等の判断をします。
更に正しい理由で保持しているか、正しい理由で売れるか。購入後の自分の行動も確認します。
(R7/5/25現在)
・・・ちなみに「現状」と書いたのは、現状で最適と思っている算出方法だからで、今後勉強を進めていく中で良いと思われる方法が出てくれば、少しずつ変えていくつもりだからです。
本日からMBAバリュエーションのシリーズで手順1〜6までを解説していきたいと思います。
それではよろしくお願いします
コメントをいただける場合は下記からお願いいたします。
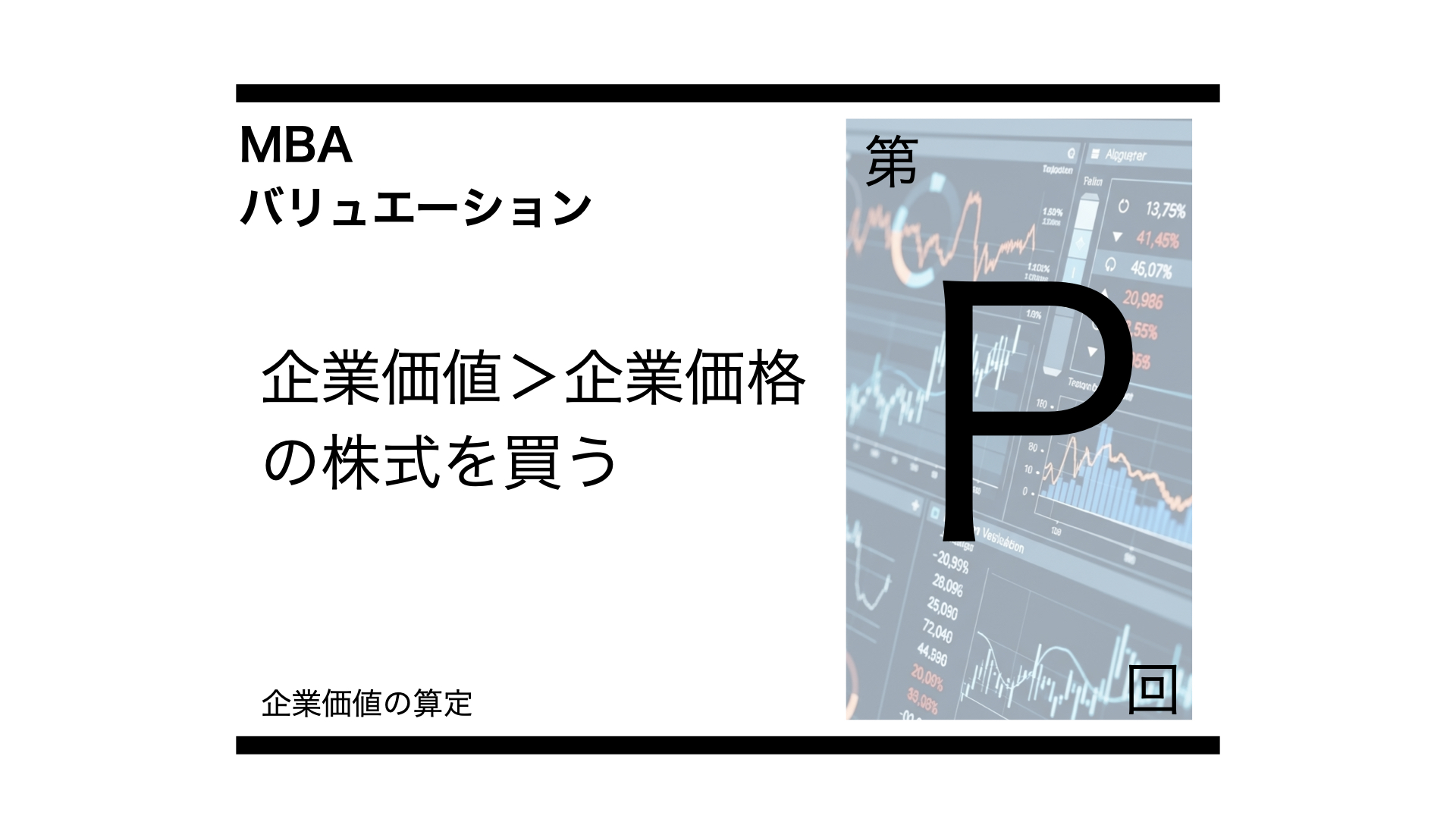


コメント